日本人なら誰もが知っている滝廉太郎の「花」
作詞作曲が「滝廉太郎(たき れんたろう)」だと思っていませんでしたか?
(戸籍名では旧字体の「瀧」)
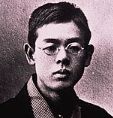
作詞は「武島羽衣(たけしま はごろも)」。
歌人・詩人であり、国語や国文学の教育にも関わった人です。

「春のうららの隅田川」という冒頭の歌詞で知られる唱歌『花』は、日本の春の美しさを象徴する名曲です。
この歌は、隅田川の風景を通じて、春の訪れの喜び、自然との対話、そしてその儚い美しさを表現しています。
朝から夜へと移り変わる時間の流れを巧みに織り込みながら、桜や柳、川を行き交う船、おぼろ月など、春を彩る情景を生き生きと描いています。
この記事では、歌詞を現代語の視点で分かりやすく解説しながら、詩人・武島羽衣が『花』に込めた思いをひも解いていきます。
歌詞の一つ一つが持つ意味を理解しながら、隅田川の春景色をより深く味わってみましょう。
「花」の歌詞の意味を現代語で

1番
春のうらゝの隅田川
のぼりくだりの船人が
櫂のしづくも花と散る
ながめを何にたとふべき
解説
「春のうらゝの隅田川」
「うらら」とは、穏やかで暖かく、のどかな春の情景を表す言葉。
このフレーズが冒頭に置かれることで、春爛漫の隅田川の光景が鮮やかに広がります。
「のぼりくだりの船人が」
隅田川は江戸時代から交通の要所であり、船が頻繁に行き交っていました。
川の往来がにぎやかであることを描写し、川の活気を感じさせます。
「櫂のしづくも花と散る」
船を漕ぐ櫂(かい)のしずくが飛び散る様子を、桜の花びらが舞い散るように表現しています。
水の動きと桜の美しさが融合し、春の隅田川の優雅な情景を強調しています。
「ながめを何にたとふべき」
これほど美しい景色を何にたとえればよいのか、と羽衣の感動が込められています。
鑑賞者の想像力を刺激する、非常に詩的な表現です。
羽衣の心情
1番では、春の隅田川の活気に満ちた美しさに対する驚嘆と喜びが込められています。
羽衣は、川の流れとともに動く風景の中で、満開の桜の美しさに心を奪われています。
船が行き交い、桜の花びらが舞う様子に「生命の躍動感」を感じながら、その感動を何かに例えることすら難しいほどの美しさだと詠っています。
春の喜びを存分に味わい、目の前の景色に心が奪われる瞬間を表現しています。
2番

見ずや あけぼの露浴びて
われにもの言ふ櫻木を
見ずや 夕ぐれ手をのべて
われさしまねく青柳を
解説
「見ずや」
「見ませんか?」という問いかけの形を取ることで、読者に直接春の美しさを呼びかけています。
「あけぼの露浴びて われにもの言ふ櫻木を」
「あけぼの」は夜明けを意味し、桜が朝露に濡れながら咲き誇る情景を描いています。
「もの言ふ」という擬人法を使うことで、桜が語りかけてくるかのような幻想的な印象を与えます。
「夕ぐれ手をのべて われさしまねく青柳を」
夕暮れ時、柳の枝が風に揺れてまるで手を伸ばして招いているように見える様子を表現しています。
桜と柳という春の象徴的な植物を対比しながら、朝と夕の異なる趣を強調しています。
羽衣の心情
2番では、春の情景に対する深い愛着と親しみが込められています。
桜の木が語りかけるように立っている様子や、柳の枝が招くように揺れる姿を通じて、自然と人との関わりを感じています。
朝の桜は静かに語りかけ、夕暮れの柳は優しく手を差し伸べる——まるで羽衣自身が春の自然に導かれ、包まれるような感覚を抱いています。
桜と柳を擬人化することで、春の美しさに対する感謝や愛おしさを表現しています。
3番

錦おりなす長堤に
くるればのぼるおぼろ月
げに一刻も千金の
ながめを何にたとふべき
解説
「錦おりなす長堤に」
「錦を織る」とは、色彩豊かな美しさを表す言葉。
満開の桜が連なる堤(堤防)が、まるで錦の織物のように美しいことを表現しています。
「くるればのぼるおぼろ月」
「くるれば」は「夜が来ると」の意味。
「おぼろ月」は春の霞がかった月のことを指し、ぼんやりとした幻想的な夜景を想起させます。
「げに一刻も千金の」
「げに」は「本当に」の意味。
「一刻千金(いっこくせんきん)」とは、わずかな時間でも千金に値するほど貴重であるという意味の言葉で、春の風景がいかに儚く、かけがえのないものであるかを強調しています。
「ながめを何にたとふべき」
1番と同じフレーズで締めくくられることで、感動の余韻を残しつつ、春の美しさを改めて問いかける構成になっています。
羽衣の心情
3番では、春の美しさの儚さと、それに対する惜別の情が込められています。
昼間の華やかな桜が、夜になるとおぼろ月の幻想的な光に照らされ、儚さを帯びていく。
この瞬間がどれほど貴重であるかを「一刻千金」という言葉で表しています。
羽衣は、春の美しさが一瞬のものであることを知りながら、その儚さこそが価値のあるものだと感じています。
最後に「ながめを何にたとふべき」と繰り返すことで、言葉では表しきれないほどの感動を読者に伝えています。
書いている場所はどこ?

「花」 の歌詞が描写している隅田川の風景は、浅草から向島(墨田区)周辺 の景色を指していると考えられます。
どうしてなのかを推測してみましょう!
隅田川の桜の名所
歌詞に登場する「櫻木」「青柳」などから、桜が咲き誇る場所であることが分かります。
隅田川の桜といえば、江戸時代から現在に至るまで有名なスポットは 向島(墨田区側) の 「隅田公園」 周辺です。
このエリアは、徳川吉宗の時代(18世紀)から桜が植えられ、庶民の花見の名所として親しまれてきました。
「のぼりくだりの船人が」
江戸時代から明治時代にかけて、隅田川は物流と観光の要所で、多くの船が行き交っていました。
特に、浅草・向島エリアでは「屋形船」や「渡し船」が盛んで、花見の季節には大勢の人が川を行き来していました。
これにより、浅草・向島周辺が歌詞の舞台である可能性が高い です。
「錦おりなす長堤に」
「長堤(ちょうてい)」とは、長く続く堤防を指します。
隅田川沿いには桜並木が続いており、「隅田堤(現在の隅田公園)」は江戸時代から花見の名所でした。
ここには川沿いに続く美しい桜並木があり、「錦を織るような美しさ」と形容するのにふさわしい場所です。
「くるればのぼるおぼろ月」
「おぼろ月」は春の霞がかった月のことで、風流な夜の情景を描いています。
隅田川の夜桜とおぼろ月の取り合わせは、江戸時代の浮世絵などにもよく描かれており、当時の花見文化と結びついている ことがわかります。
結論:浅草~向島の隅田公園周辺が舞台の可能性が高い
歌詞の描写と、歴史的な隅田川の名所を照らし合わせると、「花」は隅田公園(墨田区向島側)周辺の風景を詠んだもの と考えられます。
具体的には、吾妻橋(浅草側)から桜橋(向島側)にかけてのエリア が、歌詞のイメージに最も合致します。
現在でも、春になるとこの地域は桜の名所として賑わい、「花」の歌詞の世界を彷彿とさせる景色が広がっています。
まとめ

『花』は、日本の春の美しさを表した有名な歌です。
この記事をまとめます。
作曲は瀧廉太郎が手がけていますが、歌詞を書いたのは武島羽衣(たけしま はごろも)という詩人です。
この歌では、桜や柳、隅田川を行き交う船、そして夜にぼんやりと光るおぼろ月といった春の風景がえがかれています。
春がやってきた喜びと、その美しさがすぐに過ぎてしまうはかなさが表現されています。
歌詞を詳しく見ていくと、1番では川のにぎやかさと桜の華やかさ、2番では朝と夕の風景の変化、3番では春の夜の幻想的な雰囲気が伝わってきます。
羽衣は、この景色のあまりの美しさに心を打たれ、「何にたとえればよいのだろう」と驚きと感動を歌っています。
また、春の一瞬の輝きを大切に思い、そのはかなさを惜しむ気持ちもこめられています。
この歌の舞台は、東京の隅田川沿いの浅草から向島(墨田区)にかけてのエリアだと考えられています。
ここは江戸時代から桜の名所として知られ、今でも多くの人が花見に訪れます。
『花』は、ただ春をほめたたえるだけでなく、時間の流れとともに移り変わる風景を美しく表現した歌です。
歌詞の意味を知ることで、さらに深く春の景色を楽しめるかもしれません。
この歌を口ずさみながら、隅田川の春に思いをはせてみてはいかがでしょうか。


